TOP > NextStageメンバー活動 > 2018年度
NextStageメンバー活動
2018年度
2018年12月18日に「J-Win Next Stage 第6回定例会」が行われました。
2019/04/16
「J-Win Next Stageネットワーク 第6回定例会」を、2018年12月18日(火)に機械振興会館、J-Win淀屋橋(大阪中継会場)で開催し、69名のメンバーが参加しました。
 |
■クリエイティブな発想から新たな時代を創造
今回は、東京藝術大学名誉教授の三田村 有純氏を講師に迎え、「日本の藝術産業が未来を創る」と題した講演を行いました。
日本の漆器がヨーロッパで高い評価を受けた背景や歴史、クリエイティブな発想でのものごとに取り組むことの大切さについて、わかりやすくお話しいただきました。講演後には、参加者から「変化を意識する中でも、これだけは変えないということはあるか」という質問に対して、「周りの人に支えられていることに感謝すること」とお答えいただき、あらゆる領域に共通する考えに参加者の多くが共感し、ビジネスの発想にもつながる講演でした。
 |
 |
以下に講演の様子をダイジェストでご紹介します。
(*肩書き等は講演当時のものです。)
「日本の藝術産業が未来を創る」
東京藝術大学名誉教授 三田村 有純 氏
●女性が中心となって活躍していた縄文時代
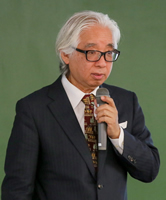 私たちが未来を創造していく上で、まずは今を創ってきた歴史について学ぶことが大切です。今から16,500年前の縄文時代の日本は、最も住みやすかったと言われています。当時の日本では、たくさんの人が住み、さまざまな物を作って暮らしていました。そこで中心となって物を作り出していたのは女性です。男性は狩りに出かけ、女性は生活に必要な物をクリエイティブな感性を働かせて生み出していた時代でした。今思えば、日本の縄文時代こそ、ダイバーシティの原点であったのではないでしょうか。また、日本の漆芸も縄文時代からの長い歴史があります。漆の樹液を木から採取して精製し、顔料を入れた色漆を作るなど、縄文時代から今の漆芸技法と変わらない技術を持っていました。漆の樹液が温度と湿度で固化することを発見した縄文人は、有益な素材として使用していたことがわかります。矢尻と矢柄をつないだり、土器を修復したりするための接着剤、土の器や木の器、編み籠などの内外を塗る塗料、土や木の粉を混ぜた粘土状のもので造形する造形素材、朱漆、黒漆で渦巻き模様などを描く絵画材料 など、幅広い目的で活用されていました。
私たちが未来を創造していく上で、まずは今を創ってきた歴史について学ぶことが大切です。今から16,500年前の縄文時代の日本は、最も住みやすかったと言われています。当時の日本では、たくさんの人が住み、さまざまな物を作って暮らしていました。そこで中心となって物を作り出していたのは女性です。男性は狩りに出かけ、女性は生活に必要な物をクリエイティブな感性を働かせて生み出していた時代でした。今思えば、日本の縄文時代こそ、ダイバーシティの原点であったのではないでしょうか。また、日本の漆芸も縄文時代からの長い歴史があります。漆の樹液を木から採取して精製し、顔料を入れた色漆を作るなど、縄文時代から今の漆芸技法と変わらない技術を持っていました。漆の樹液が温度と湿度で固化することを発見した縄文人は、有益な素材として使用していたことがわかります。矢尻と矢柄をつないだり、土器を修復したりするための接着剤、土の器や木の器、編み籠などの内外を塗る塗料、土や木の粉を混ぜた粘土状のもので造形する造形素材、朱漆、黒漆で渦巻き模様などを描く絵画材料 など、幅広い目的で活用されていました。●歴史の変遷とともにヨーロッパで注目された日本の漆器
日本の漆器は、ヨーロッパの文化にも影響を与えています。15世紀から20世紀の間に、ヨーロッパの人たちは中国と日本文化に非常に憧れを持っていました。フランス語で「CHINOISERIE 」は中国趣味、「JAPONISME」は日本趣味を表します。また、イギリス(英語)では、chinaに磁器(白色の宝石)、japanに漆器(黒色の宝石)の意味があり、磁器を示す「BONE CHINA」、漆器を示す「JAPANING」などの言葉も生み出されました。ヨーロッパで漆工芸産業が起きたのには、いくつかの歴史的経緯 があります。1つは1543年にポルトガル人が種子島に来航したことを機に、日本から南蛮漆器がヨーロッパに渡ったことです。当時の日本は織田信長、豊臣秀吉の時代です。繊細で美しい蒔絵を施した日本の漆器が海を渡り、注目されるようになりました。2つ目はオランダの台頭です。後にスペインやポルトガルに代わってオランダやイギリスが世界を回るようになります。ここでは、キリスト教も少し影響しています。 華やかな装飾を好むカトリックに対して、プロテスタントはベーシックなものを好む文化があります。カトリックの国であるスペインやポルトガルに対して、プロテスタントの国・オランダがこれまでとは違ったデザインの漆器をヨーロッパに持ち込みました。3つ目は、イギリスで独自の文化が生まれたことです。江戸時代に日本はイギリスとの交易を絶ったため、日本の漆器を購入できなくなったイギリスは、交易をしていた中国製作の描金(消粉蒔絵)を輸入して、「広東蒔絵」としてヨーロッパに広めました。日本や中国の真似をして作られた作品が、ヨーロッパに新たな藝術文化を生み始めたのです。その後、江戸末期から明治にかけて、パリ、ロンドン、ウイーンなどで万博が開催され、漆芸や彫金、日本画、木彫など日本の藝術作品は、世界に広まっていきました。
●日々クリエイティブに仕事に取り組み、本質を見極める力を
日本の伝統工芸産業をどのよう継承していくかというのは大きな課題です。一方で、藝術こそ新しい革命が起こせると考えています。絵を描いたり、彫刻をしたりすることが藝術ではなく、クリエイティブに作り出す感性を持ち、新たなものを生み出すことが時代を創造できるということです。かつて人類の歴史においては、農業革命や産業革命、コンピューター革命などにより時代を大きく進化させてきました。次に来るのは、伝統産業力や素材力、技術力などを進化させることによって世の中を変えていく、藝術を通した革命ではないかと考えています。「先代と同じ事はするな。考え方の基礎を別な所に求めよ。技法は学び、図案は真似るな。自分で新しい技法を作り出す事。時代の先を行く事」が、代々江戸蒔絵に携わってきた三田村家の家訓です。皆さんの仕事も、ルーティンワークの繰り返しではなく、次の世代の人を育てるために日々クリエイティブに取り組んでいるのではないでしょうか。人を育て、日本の新しい時代を創造していくためには、あらゆる領域において本質が何かを見極める力が必要です。そのためにもたくさんの本物に触れ、本物を見分ける力をつけてほしいと願っています。
~講演の感想~
- 歴史、藝術、ダイバーシティの関係性が体系立てて理解できた
- 「本物を見分ける力が未来を創る」という言葉が印象的だった。本物にふれるために足を運ぶこと・労をいとわないこと、「知っている気になって」終わることのないようにしたい
- まわりの人を大切にすること、特に下位職に対する気持ちの持ち方を変えたいと改めて感じました
- 日本人の思考に響くのは、和語(訓読み)である、ということを今後のプレゼンに生かせる。衣食足りてこそクリエイティブになれる、ということで働き方改革を確実に実現すべきであることがわかった
【三田村 有純 氏のPROFILE】
1949年 東京都杉並区生まれ。江戸蒔絵赤塚派 八代 祖父 自芳氏、 九代 父 秀雄氏より蒔絵技法他を学ぶ。東京藝術大学 名誉教授、江戸蒔絵赤塚派十代継承、公益社団法人 日展 理事(審査員6回)、一般社団法人 現代工芸美術家協会 理事、一般社団法人 国際文化研究院 理事長等を努め、美術団体 九つの音色 同人 漆藝を専門とし、数々の作品を発表する傍ら、国際交流にも尽力。 著書に、「藝術がいづる国・日本」「漆とジャパン 美の謎を探る」「お箸の秘密」など。
