メンバー活動
2019年度
2019年8月2日に「J-Win第9期High Potentialネットワーク 8月度定例会」が行われました
2020/01/22
「J-Win第9期High Potentialネットワーク 8月度定例会」を、2019年8月2日(金)に機械振興会館、大阪中継会場、福岡中継会場で開催し、計207名のメンバーが参加しました。
■社会を変えるTechnologyに人がどのように関わっていくかを考える
8月度定例会のテーマは「Technologyを理解し、Technologyが いかに社会を、経済を、会社を大きく変えるかを知る」。
日本アイ・ビー・エム株式会社の石川 繁樹氏を講師に迎え、「未来を拓くIBM研究最前線 Cognitive Computing」と題した講演を行いました。人工知能の研究の歴史や最新の技術、IBMが取り組んできたWatson技術を応用した事例など、Technologyによって広がる可能性についてわかりやすく解説していただきました。
「AIには踏み込めない領域はあるのか」という参加者からの質問に対しては、「どんなにすぐれたAIでも、データが正しくなければ誤った結果を出してしまう。その検証は人間にしかできない」とお答えいただき、AIと人との関り方についてもあらためて考える機会になりました。
 |
 |
以下に講演の様子をダイジェストでご紹介します。
※社名・肩書は実施当時のものです
「未来を拓くIBM研究最前線 Cognitive Computing」
日本アイ・ビー・エム株式会社
研究開発(IBM Tokyo Laboratory) アカデミック・アドボケート担当
部長 工学博士 石川 繁樹 氏
●1960年代から時代ごとに研究されてきたテーマが進展し、さらに応用分野へと発展
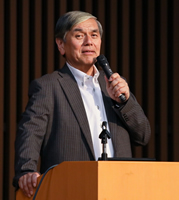 人工知能の研究は1960年代の第一次ブームに始まり、70年代後半から90年代後半の第二次ブームの頃に非常に盛んになりました。21世紀に入り、コンピュータの性能の進化とともに、第三次AIブームが起こり、さまざまな活用の可能性が広がってきています。それぞれの時代に研究されているテーマは少しずつ違いますが、徐々に進展し、解明された事実をもとにさらに新しい応用分野へと研究が進められています。こうした人工知能のTechnologyの中で、最近特に注目されているのが深層学習「ディープラーニング」です。ディープラーニングは、第二次ブームの時代に、コンピュータに知識を蓄積していくことで人間のように知恵をつけることができないかと研究された「機械学習」が基礎になっています。これに多段階のネットワークを使ったものがディープラーニングに分類されており、現在の第三次ブームのホットエリアです。具体的には、チェスや将棋、囲碁の名人に挑むコンピュータや、決まった動きだけではなく状況に応じて判断して動作する産業用ロボット、高齢化社会に向かう中で注目されている自動車の自動運転、音声認識の技術を応用したAIスピーカーなども身近になっています。さらに、企業の複雑な経営判断に必要な情報を的確に提供し、正しい判断に導くことへの支援にも人工知能が活用される時代に入っています。
人工知能の研究は1960年代の第一次ブームに始まり、70年代後半から90年代後半の第二次ブームの頃に非常に盛んになりました。21世紀に入り、コンピュータの性能の進化とともに、第三次AIブームが起こり、さまざまな活用の可能性が広がってきています。それぞれの時代に研究されているテーマは少しずつ違いますが、徐々に進展し、解明された事実をもとにさらに新しい応用分野へと研究が進められています。こうした人工知能のTechnologyの中で、最近特に注目されているのが深層学習「ディープラーニング」です。ディープラーニングは、第二次ブームの時代に、コンピュータに知識を蓄積していくことで人間のように知恵をつけることができないかと研究された「機械学習」が基礎になっています。これに多段階のネットワークを使ったものがディープラーニングに分類されており、現在の第三次ブームのホットエリアです。具体的には、チェスや将棋、囲碁の名人に挑むコンピュータや、決まった動きだけではなく状況に応じて判断して動作する産業用ロボット、高齢化社会に向かう中で注目されている自動車の自動運転、音声認識の技術を応用したAIスピーカーなども身近になっています。さらに、企業の複雑な経営判断に必要な情報を的確に提供し、正しい判断に導くことへの支援にも人工知能が活用される時代に入っています。●医療分野での診断に人工知能を活用し、病気の早期発見や適切な治療への期待も
では、人工知能を活用することで、世の中はどのように変わるのでしょうか。産業ロボットの高度化や、自動運転の実現などとともに、注目されているのが医療分野での活用です。多岐にわたる症例について、専門の先生が長年の経験と知識に基づいて診断する従来の方法に、高度な情報を加えて診断を支援するという動きがあります。例えば、ゲノム情報から一人一人の病状に応じた的確な薬を見つけ出すなど、さまざまなトライアルも始まっており、些細な体の異変から早期に病気を発見することも期待されています。また、これからの時代で重要な要素になるのが、ビッグデータです。2025年には全世界のデータ量が165ゼタバイト(*ゼタバイト=10の21乗バイト)という天文学的な数字に達するとも言われています。この大量のデータをどのようにハンドリングしていくかという点もこれからの大きな課題です。
●IBMのWatson技術で事業展開を推進
IBMでは、アメリカの人気クイズ番組「Jeopardy!(ジョパディ)」の歴代チャンピオンにコンピュータが挑戦する「IBM Watson」というプロジェクトを2011年に展開しました。機械学習の技術を備えたコンピュータが人間に圧勝したことで、人工知能(AI)の誕生かと、世界中から注目されました。しかしIBMは、あえてAIという言葉は使わずに、認知科学(コグニティブ・サイエンス)のサイエンスをコンピューティングに置き換えた「コグニティブ・コンピューティング・システム」と呼びました。IBMではこのプロジェクトで培った技術をもとに、「顧客接点改革」「探索・発見」「意思決定支援」という3つの領域において事業を展開しています。例えば、コールセンターを設置している企業も多いかと思いますが、ベテランオペレーターのような知識やスピードを誰もがすぐに身につけられるわけではありません。あるメガバンクでは、Watson技術を応用し、顧客からの問い合わせ内容に応じて回答例を表示したり、進度によって順番を変えたりするなど、オペレーターを支援するシステムを導入し、サービスクオリティの向上に役立てられています。
●AIで何を解決したいのか、課題を明確にすることが重要
これからますます新しいTechnology開発が進んでいくと思いますが、人間がAIをどのように使っていくかということも重要です。AIは、数多くのデータを学習させていますので、データに間違いがあると正しく機能することができません。データをきちんと整理して正しい学習を行い、データの種類によって分析するTechnologyや、ソフトウェアをどのように組み合わせるかという点も大きなポイントになります。AIは何でもできるように思いがちですが、まずはAIで何を解決したいのか、課題を明確にすることが大切です。今後はAIの活用を適切に推進することができるリーダーの存在も重要になってくると思います。ぜひテクノロジーの進化に注目し、みなさんのビジネスにも上手に活用していってください。
~参加者の感想 ~アンケートコメントより~
- テクノロジーの進化がもたらすメリットばかりに目がいっていたが、デメリットもあることを認識した。また、そういった社会で「人間」がどうあるべきかを検討する機会となった
- 経営判断にもAIが介入することが想定されるという話を聞き、AIを脅威に感じるのではなく、有効に活用する視点で捉えなければならないのだという、マインドチェンジの機会になった
- 課題の発掘などは人が担うという話が印象に残った。引き続き育成の手は緩めずに取り組もうと感じた
- AIの進歩に伴い、データの問題点(データ取得、出所)等、データ基盤の重要性が印象に残った。AI時代だからこそ、 潜むリスクへの対応が重要であると感じた
 |
 |
【石川 繁樹 氏のPROFILE】
1985年日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所に入社後、 基礎研究、開発企画部門、ソリューション営業などを経験した後 IBM Tokyo LabにてIBMのテクノロジーを活用したビジネス展開をリード 現在、研究開発・アカデミック・アドボケートを担当。慶応義塾大学大学院Leading大学院特任教授を兼任。
