TOP > Executiveメンバー活動 > 2019年度
Executiveメンバー活動
2019年度
2019年7月17日にJ-Win Executive ネットワーク7月度定例会が行われました。
2019/10/23
「J-Win Executive ネットワーク7月度定例会」を、2019年7月17日(水)に港区のアークヒルズで開催し、33名のメンバーが参加しました。
 |
定例会第一部では、Executiveネットワーク活動での連絡事項に続き、内永理事長による講話が設けられました。
●J-Winの三層女性ネットワークを企業の中にも
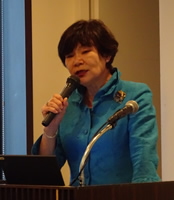 日本の女性活躍推進をグローバルと比較すれば、そのスピードは遅いと言わざるを得ない。もっと多くの女性が企業の意思決定が出来る役職に登用されなければならないが、現実は管理職に上がったとたんに放り出され強い孤独感を味わう。だから女性管理職はなかなか育たない。
日本の女性活躍推進をグローバルと比較すれば、そのスピードは遅いと言わざるを得ない。もっと多くの女性が企業の意思決定が出来る役職に登用されなければならないが、現実は管理職に上がったとたんに放り出され強い孤独感を味わう。だから女性管理職はなかなか育たない。J-Winでは女性管理職を支える三層のネットワーク活動をおこなってきた。これと同じように、企業の中にも相互に助け合い、心の支えとなり、安らぎを与えられる女性ネットワークをつくってほしい。三層からなる三角形の軸を太くして、いろんな意見を自由に言える、発想が豊かになる、そんなカルチャーを女性たちがつくっていけば、男性たちにも変化が起こる。
Executive、Next Stage、High Potentialネットワークといった三層構造を各企業に構築する必要があり、そのためにもExecutiveネットワークメンバーがリーダーシップを発揮することを期待したい。
●誰もが人と関わりながら社会参加することを支援するロボット開発を推進
定例会第二部では、株式会社オリィ研究所 吉藤 健太朗氏を講師に迎え、「社会的課題の解決」と題した講演を行い、遠隔操作により作動する分身型コミュニケーションロボット「OriHime」によって実現できたこと、そして未来への展望についてお話しいただきました。AI技術が急速に進む中でも、「人は人にしか癒やされない」という視点に立ち、人の気持ちに寄り添いながら社会的課題の解決に向けてロボット作りに取り組む姿勢からは、多くの気づきを得ることができました。
参加者からは、今後の活動についての質問があり、「必要とされている方に、こういう選択肢があるということを広く知ってもらいたい」と、支援が必要な人に届けることの難しさについても問題提起されました。
以下に講演の様子をダイジェストでご紹介します。
(*肩書き等は講演当時のものです)
「社会的課題の解決」 ~誰もが自由に社会参加できる世界の実現~
株式会社オリィ研究所 共同創設者 代表取締役 CEO
吉藤 健太朗 氏
●支援を必要とする人に寄り添った研究を決意
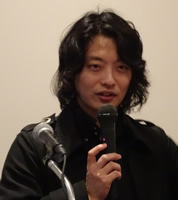 今一人暮らしの高齢者は1000万人を超え、病気が理由で学校に通えない人は6万人、18歳以下の引きこもりは14万人いると言われています。こうした人たちがどうしたら孤独にならずに社会参加できるかということを考えながらロボットの研究に取り組んでいます。
今一人暮らしの高齢者は1000万人を超え、病気が理由で学校に通えない人は6万人、18歳以下の引きこもりは14万人いると言われています。こうした人たちがどうしたら孤独にならずに社会参加できるかということを考えながらロボットの研究に取り組んでいます。実は、私自身も病気がきっかけで学校に通えなくなった引きこもりの時期がありました。そんな私に母がロボットの大会への参加を勧めてくれ、中学2年生の時に全国大会で準優勝したことが現在の仕事の原点になっています。その後、尊敬する先生のいる地元の工業高校に進学して、車椅子づくりに取り組み、2005年にアメリカで開催されたインテル国際学生科学技術フェア(ISEF)に日本代表として出場し、3位に入賞することができました。この時、世界の高校生たちとの交流の中で、彼らが目を輝かせて夢を熱く語る様子に圧倒されながら、自分は何がしたいのかわからないでいました。
そんなある日、面識のない広島のおばあちゃんから「世界3位になった高校生に作ってほしいものがある」と電話がかかってきました。話を聞くと、足腰の悪いおばあちゃんが普段体を動かす際などに娘さんに手助けしてもらうのを申し訳なく感じており、できるだけ娘さんに負担をかけない"ローラー付きの座布団"を作ってほしいという依頼でした。
私はそれまで、車椅子にいろいろな機能を付けることを研究していましたが、おばあちゃんの話を聞いて、実際に車椅子を必要としている人がどんな暮らしをしているのかということについて理解していないことを気づかされました。そして、体の不自由な人が周りに迷惑をかけたくない、自分は無力だと感じてしまうような課題を解決するための研究に人生をかけてみようと決意したのです。
●人工知能を学んだ結果、人は人にしか癒やされないことを再認識
 最初に考えたのは、話し相手になるようなロボットがいたら良いのではないかということ。それには人工知能を学ぶ必要があると思い、香川の高専に編入しました。そこでの人工知能の研究そのものはとても楽しかったのですが、次第に、人の孤独を解消し癒やしてくれるのは人工知能ではないと感じるようになりました。例えば、引きこもってしまったときに、話し相手になってくれる人工知能を備えたロボットがいたら孤独を解消してくれるでしょうか。私自身の経験を振り返っても、両親や数少ない親友、学校の先生、車椅子づくりを教えてくれた師匠、世界の高校生、広島のおばあちゃんなど、人生の転機には「人」がいました。人は時にはストレスになることもありますが、人は人にしか癒やされないというのが、人工知能を研究した私の結論です。
最初に考えたのは、話し相手になるようなロボットがいたら良いのではないかということ。それには人工知能を学ぶ必要があると思い、香川の高専に編入しました。そこでの人工知能の研究そのものはとても楽しかったのですが、次第に、人の孤独を解消し癒やしてくれるのは人工知能ではないと感じるようになりました。例えば、引きこもってしまったときに、話し相手になってくれる人工知能を備えたロボットがいたら孤独を解消してくれるでしょうか。私自身の経験を振り返っても、両親や数少ない親友、学校の先生、車椅子づくりを教えてくれた師匠、世界の高校生、広島のおばあちゃんなど、人生の転機には「人」がいました。人は時にはストレスになることもありますが、人は人にしか癒やされないというのが、人工知能を研究した私の結論です。その後、早稲田大学での研究を経て、自分の研究室を立ち上げるに至りました。そこで自分で作ったのが「OriHime」というロボットです。「OriHime」は、人工知能や音声認識ではありません。カメラとスピーカーが内蔵され、人が自宅や病院のベッドから遠隔操作することができます。たとえばリアルタイムで学校の黒板を見ることができて先生の話が聞けて、手を上げて発言することもできる、もう一つの分身として機能するロボットです。また、病気と闘っている人だけでなく、育児中の女性が"OriHime出社"をして仕事を続けることも支援しており、既に企業での活用が進んでいます。
●人と出会いながら誰かのために役立てることを支援するロボットに
 私の会社では、「OriHime」を使って働いているメンバーもいて、今日の講演会にも一緒に来てもらっています。病院で過ごしている人が、外に出て名刺交換をして知り合いが出来たり、シンポジウムに参加したりすることもできます。テレビ電話と違うのは、その瞬間だけではないという点です。常に私と一緒にいるので、タクシー移動をしながら雑談をしたり、隣で相槌を打ったりすることもできます。また、ALS(筋萎縮性側索硬化症)という病気を知ってから、目の動きだけで「OriHime」を操作する研究にも取り組んでいます。将来は、ALSで頷くことしかできなかった人が、目の動きによって自由に走り回り、自分の意思で近くにいる人にコーヒーを入れたり、荷物を受け取ったり、自分の事だけではなくて誰かの役にたてるようなロボットに育てていくことが目標です。
私の会社では、「OriHime」を使って働いているメンバーもいて、今日の講演会にも一緒に来てもらっています。病院で過ごしている人が、外に出て名刺交換をして知り合いが出来たり、シンポジウムに参加したりすることもできます。テレビ電話と違うのは、その瞬間だけではないという点です。常に私と一緒にいるので、タクシー移動をしながら雑談をしたり、隣で相槌を打ったりすることもできます。また、ALS(筋萎縮性側索硬化症)という病気を知ってから、目の動きだけで「OriHime」を操作する研究にも取り組んでいます。将来は、ALSで頷くことしかできなかった人が、目の動きによって自由に走り回り、自分の意思で近くにいる人にコーヒーを入れたり、荷物を受け取ったり、自分の事だけではなくて誰かの役にたてるようなロボットに育てていくことが目標です。たとえ病気で寝たきりになっても、あらゆる人たちが友人と出会い、同僚と助け合い、誰かに必要とされながら生きていける、彦星と織姫のように会いたい人に会いに行ける未来を実現していきたいと願っています。
【吉藤 健太朗氏のPROFILE】
高校時代に電動車椅子の新機構の発明に関わり、2004年の高校生科学技術チャレンジ(JSEC)で文部科学大臣賞を受賞。翌2005年にアメリカで開催されたインテル国際学生科学技術フェア(ISEF)に日本代表として出場し、グランドアワード3位に。 高専で人工知能を学んだ後、早稲田大学創造理工学部へ進学。自身の不登校の体験をもとに、対孤独用分身コミュニケーションロボット「OriHime」を開発(この功績から2012年に「人間力大賞」を受賞)。 開発したロボットを多くの人に使ってもらうべく、株式会社オリィ研究所を設立。自身の体験から「ベッドの上にいながら、会いたい人と会い、社会に参加できる未来の実現」を理念に、開発を進めている。ロボットコミュニケーター。趣味は折り紙。

